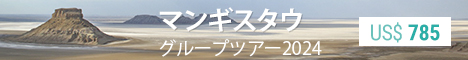カザフスタンの文学

カザフスタンの文学史は、数千年にわたる物語である。かつて、現在のカザフスタンの領土(カスピ海沿岸から雪に覆われたアルタイ山脈に至るまで)には、数多くの部族が暮らしていた。彼らは伝説や神話を語り、叙事詩を生み出し、壮大な物語を創作してきた。この時代の作品は、長い間受け継がれ、多くの人々に親しまれたことから、大衆文学と見なされている。個人の作家が独自の作品を執筆し、注目されるようになったのは19世紀半ば以降のことである。
約2000年前、カザフスタンの遊牧民たちは、神話的な英雄や神々、怪物の活躍を描いた長大な詩を作り、多くの伝説を生み出した。これらの物語は、やがて『コルクト・アタ』や『オグズ・ナメ』といった叙事詩へと発展していった。コルクトは、実在した歴史上の人物であり、叙事詩では語り手として登場するが、実際には中世の思想家であり音楽家であり、さらにカザフの伝統楽器コブズの創始者でもあった。コブズやドンブラは、こうした叙事詩を語る際の伴奏楽器としてよく用いられる。
カザフスタンの詩の伝統は、時代とともに洗練され続けてきた。15世紀には「トルガウ」という詩のジャンルが人気を博した。トルガウは、内省的な内容で、人生の教訓や道徳的な教えが込められた詩である。この詩を演じるのは「ジラウ」と呼ばれる詩人兼歌手であり、彼らは道徳や教育的な役割を果たすだけでなく、国の政治にも一定の影響力を持っていた。17世紀になると、詩はより革新的なものとなり、「アイティス」の伝統が生まれた。アイティスとは、二人の「アクィン」(詩人兼歌手)が即興で詩を交わす歌唱詩の決闘であり、現代のラップバトルにも似ている。テーマは宗教、社会問題、政治体制など、多岐にわたっていた。
カザフスタンの文学が本格的に記録されるようになったのは、19世紀前半にロシア帝国に組み込まれてからである。ロシアやヨーロッパの文学が大きな影響を与え、19世紀末にはイブライ・アルティンサリン、ショカン・ワリハーノフ、そしてカザフ文学を代表する作家アバイ・クナンバエフといった名前が広く知られるようになった。この時期、カザフ文化は世界的に有名な文学作品の翻訳によって豊かになり、カザフの作家たちは新たなジャンルや表現形式を習得し、またカザフ民話の記録作業も進められた。
20世紀に入ると、ソビエト連邦の支配のもとで、伝統的な社会主義テーマや共産党を称賛する作品が主流となった。「大祖国戦争(第二次世界大戦)」の時期には、兵士や英雄を讃える愛国的な詩が多く書かれた。20世紀後半になると、作家たちは小説やドラマを手がけるようになり、さらにSF(サイエンス・フィクション)の分野にも進出した。こうして、現代のカザフ文学は、世界の主要な文学の流れとスタイルに近いものとなった。